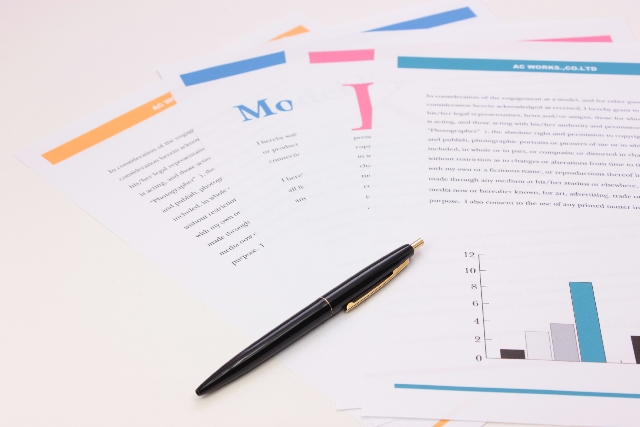


会社を定年退職したのですが、健康保険を任意継続にするか、国民健康保険にするか、妻の共済保険に入るか迷っています。
妻の共済保険に入るには条件はありますか?失業保険と厚生年金をもらう予定です。
どれを選択したら1番良いですかお教え下さい。
妻の共済保険に入るには条件はありますか?失業保険と厚生年金をもらう予定です。
どれを選択したら1番良いですかお教え下さい。
妻の扶養家族となり共済保険に入るのがお徳と思いますが、扶養家族の条件を満足(退職年の給与収入、失業保険収入、年金収入等が限度額以下になってから)
任意保険は、現役時に会社負担分が個人負担となり約二倍になります
国民保険は、退職時給与で保険料が決まります(一年間、退職後は失業保険、年金が収入額とし算定)、お住まいの自治体ホームページで国民健康保険関連で保険料検索して下さい(自治体で金額が異なりますので)
任意保険は、現役時に会社負担分が個人負担となり約二倍になります
国民保険は、退職時給与で保険料が決まります(一年間、退職後は失業保険、年金が収入額とし算定)、お住まいの自治体ホームページで国民健康保険関連で保険料検索して下さい(自治体で金額が異なりますので)
就職活動にあたって
平成19年以降、短期の派遣で繋ぎつつ、平成25年10月をもって完全無職になり失業保険受給中の47歳です。
社員や契約社員などや派遣でも長期雇用にはなってはいませんでしたが、ここまで無職だった事は無く、しかしながら、現在は持病(前癌による子宮全摘出)の為に就業を見合わせて、半年ある失業保険の力を借りております。
ですが、自活をしている為に今後も働かなくてはいけません。
面接の際に必ず
「離職後は何をされてましたか?」
と質問されるかと思います。
その際に
「失業保険を受給してました」
とだけ答えれば、大丈夫でしょうか?
それとも
「いい機会なので失業保険を受給しながら、気になっていた婦人系の治療をしていました」
と言う様な事を伝えた方がいいのでしょうか?
どうか皆様のお知恵をご伝授下さい。
宜しくお願い致します。
平成19年以降、短期の派遣で繋ぎつつ、平成25年10月をもって完全無職になり失業保険受給中の47歳です。
社員や契約社員などや派遣でも長期雇用にはなってはいませんでしたが、ここまで無職だった事は無く、しかしながら、現在は持病(前癌による子宮全摘出)の為に就業を見合わせて、半年ある失業保険の力を借りております。
ですが、自活をしている為に今後も働かなくてはいけません。
面接の際に必ず
「離職後は何をされてましたか?」
と質問されるかと思います。
その際に
「失業保険を受給してました」
とだけ答えれば、大丈夫でしょうか?
それとも
「いい機会なので失業保険を受給しながら、気になっていた婦人系の治療をしていました」
と言う様な事を伝えた方がいいのでしょうか?
どうか皆様のお知恵をご伝授下さい。
宜しくお願い致します。
パートなどの採用経験者です。
まず、あなたは今まで仕事をつないできたということで、
それなりのスキルと、対人能力があると思います。
そこで、面接側ではなぜ中断と言うことは、気にすると思います。
病気のことは正直に言った方が良いと思います。
まず一つは、上に書いたように
「このような人が仕事していないのはなぜ?」
と言う疑問で、もっと悪いことを観がさせるよりは、あっさり病気のことを言えば
すっきりします。
もう一つ言うと、私の姉も子宮筋腫のため、子宮摘出してその後更年期障害が
発生して苦しみました。
採用時に病気のことを言っていた人の、発病に関しては、採用側も理解があります。
一方、黙っていた病気に関しては、結構採用後も風当たりがきつくなります。
こういうことも考えてください。
まず、あなたは今まで仕事をつないできたということで、
それなりのスキルと、対人能力があると思います。
そこで、面接側ではなぜ中断と言うことは、気にすると思います。
病気のことは正直に言った方が良いと思います。
まず一つは、上に書いたように
「このような人が仕事していないのはなぜ?」
と言う疑問で、もっと悪いことを観がさせるよりは、あっさり病気のことを言えば
すっきりします。
もう一つ言うと、私の姉も子宮筋腫のため、子宮摘出してその後更年期障害が
発生して苦しみました。
採用時に病気のことを言っていた人の、発病に関しては、採用側も理解があります。
一方、黙っていた病気に関しては、結構採用後も風当たりがきつくなります。
こういうことも考えてください。
健康保険の扶養と、失業手当の質問です
知人からの代理で質問します
知人(男性)の会社は健康保険組合はありません、協会けんぽです。
その妻は、いったん夫の扶養に入りつつ、失業保険を受給することは可能でしょうか。
働く予定はあり、働くといってもパートの予定で、年間130万をこえる見込みはありません。
ハローワークで失業保険を受給申請する時に、そもそもけんぽの扶養に入ってるかどうかなんてばれるもんですかね?
知人からの代理で質問します
知人(男性)の会社は健康保険組合はありません、協会けんぽです。
その妻は、いったん夫の扶養に入りつつ、失業保険を受給することは可能でしょうか。
働く予定はあり、働くといってもパートの予定で、年間130万をこえる見込みはありません。
ハローワークで失業保険を受給申請する時に、そもそもけんぽの扶養に入ってるかどうかなんてばれるもんですかね?
失業保険を貰う場合には月額が130万/12の金額以下でしたら、扶養に入れると思います。
健保では「扶養に入れる際に収入の確認」をすると思います。言い方を変えれば扶養に入った後に被扶養者が上記の金額を超える失業保険を貰っているかどうかは確認する機会が無いと思われます。ハローワークはどこの健保に入っているかはそもそも確認しないと思います。
健保では「扶養に入れる際に収入の確認」をすると思います。言い方を変えれば扶養に入った後に被扶養者が上記の金額を超える失業保険を貰っているかどうかは確認する機会が無いと思われます。ハローワークはどこの健保に入っているかはそもそも確認しないと思います。
雇用保険のある会社に勤めた方がいいと思いますか?
パートを探しています。現状としてはフルタイムで働くつもりはありません。週15~30ぐらいで…と思っています。
20時間を超えないと雇用保険には加入できないし、超えたとしても中には加入していない企業もあります。
気になる会社があっても雇用保険に加入していないと応募をためらってしまいます。
以前フルタイムで数年働いていたのですが、契約時に20時間を超えない内容で契約書を作った為、雇用保険未加入のままでした。その後突然倒産してしまったのですが、もちろん失業保険は受けられず急に厳しい生活になりました。
辞めたり、倒産しなければ雇用保険は入らなくてもいいのですが、このことを考えると、重視した方がいいのかとも思います。
それともあまりこだわらずよさそうな会社があれば応募してみた方がいいのでしょうか?
皆様だったらどうしますか?よければご意見ください。
パートを探しています。現状としてはフルタイムで働くつもりはありません。週15~30ぐらいで…と思っています。
20時間を超えないと雇用保険には加入できないし、超えたとしても中には加入していない企業もあります。
気になる会社があっても雇用保険に加入していないと応募をためらってしまいます。
以前フルタイムで数年働いていたのですが、契約時に20時間を超えない内容で契約書を作った為、雇用保険未加入のままでした。その後突然倒産してしまったのですが、もちろん失業保険は受けられず急に厳しい生活になりました。
辞めたり、倒産しなければ雇用保険は入らなくてもいいのですが、このことを考えると、重視した方がいいのかとも思います。
それともあまりこだわらずよさそうな会社があれば応募してみた方がいいのでしょうか?
皆様だったらどうしますか?よければご意見ください。
雇用保険は個人でも加入できるという回答がありましたがそれは出来ません。あくまでも会社が手続きをします。
週20時間以上で31日以上雇用なら雇用保険法で会社は加入する義務があります。
また、働く人も不幸にして失業した場合は当座の収入源になりますから加入したほうが賢明です。
保険料率は会社が0.85%の負担で個人は0.5%(10万円で600円)の負担ですから大きな金額ではありません。
補足:下の方の回答はは間違いです。
週20時間以上で31日以上雇用なら雇用保険法で会社は加入する義務があります。
また、働く人も不幸にして失業した場合は当座の収入源になりますから加入したほうが賢明です。
保険料率は会社が0.85%の負担で個人は0.5%(10万円で600円)の負担ですから大きな金額ではありません。
補足:下の方の回答はは間違いです。
関連する情報